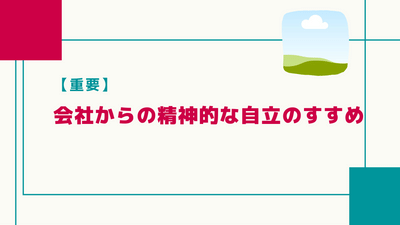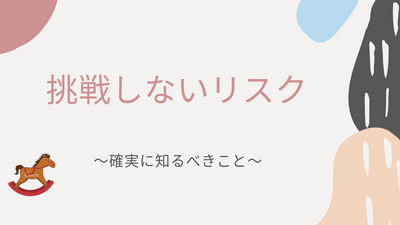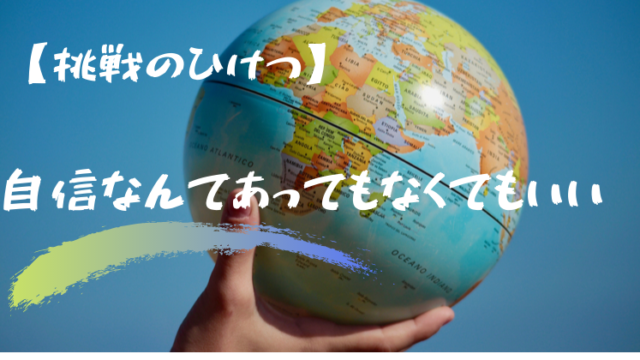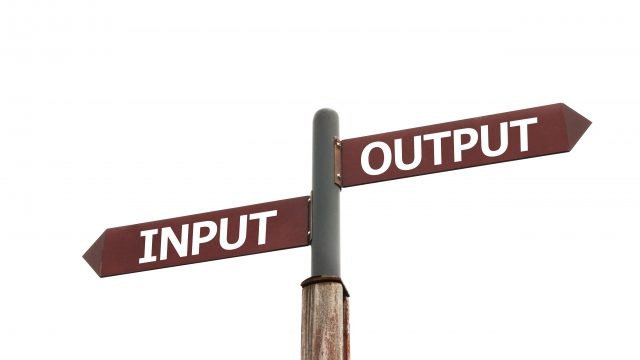この記事では“伝わる言葉”をテーマしています。
「言いたいことはあるのになかなか上手く言葉にならない」
「相手に考えが伝わっているか不安。。」
「部下や同僚に自分の意思が伝わらない」
「他人と会話が成り立たない」
こんな悩みを抱えていませんか。
改善しようとしているになかなか思い通りにならない。
そんな人に是非読んでもらいたいです。
“伝わる言葉”をマスターすれば、確実に相手に自分の意思が伝えられるようになります。むしろ、自分が思っている以上に意思が伝わるようになります。
日本のトップコピーライター 梅田悟司氏の著書「言葉にできる」は武器になるという本の内容を基に“伝わる言葉”について紐解いてみましょう。
梅田 悟司 日本のトップコピーライター
代表作
リクルートのタウンワーク「バイトをするならタウンワーク」
缶コーヒージョージア 「世界は誰かの仕事でできている」
コミュニケーションの4段階
まず、私たちが言葉を伝えている時、聞き手の理解度には段階があるそうです。自分が聞き手の時のつもりで、お読みください。
①不理解・誤解
こちらの内容が伝わっていない、もしくは誤って伝わっている状態。
発信者と受信者で認識のズレが生じている。
②理 解
伝えた内容が過不足なく、伝わっている状態。
ただ、理解以上の解釈が行われているわけではなく、「頭では分かっているが、心がついていかない」といった状況に陥りやすい。
③納 得
相手が話した内容が頭で理解しただけでなく、内容が腹に落ちている状態。
「理解」に比べて自分ゴトとして捉えることが出来ている。
「なるほど」「確かに」といった感情を伴うことが多い。
④共 感・共 鳴
見聞きした内容を理解した上で、心が動かされ、自らの解釈が加わっている状態。
自分なりの考えを加えたり、自分に出来ることがないかと協力を申し出るといった行動を起こしたくなっている。
私たちのコミュニケーションを振り返った時にドキッとしませんか。
なかなか③納得にまで達しているケースは多くないと思います。
自分がどの段階の表現が出来ているのか。伝えるって奥が深いですよね。
伝わり方は人間性の評価につながる
さらに、日常生活を思い返してみましょう。
相手の言葉に対して何も感じ取ることが出来なかった場合、意味が分かりにくかった時、先ほどの4段階の1つ目や2つ目の印象を持ったときみなさんは、どのような感情を抱きますか。
「言葉づかいが下手だな」
「もっと上手に表現できないのかな」
「薄っぺらな考えだな」
「伝えたいことがまとまっていないな」
「深く考えていないな」
などといった話し手の人間性に対して感情を抱いてしまうことありませんか。
つまり、人間は相手の言葉に宿る重さや軽さ、深さや浅さを通じて、その人の人間性そのものを無意識のうちに評価しているようです。
内なる言葉の存在
では、どうしたら、先のような感情を抱かせることなく、伝えたいことを伝えられるようになるのか。
そこで登場するのが、、、
『内なる言葉』の存在です。
内なる言葉とは、外に発することない、自分が自分と会話をするときに無意識に使っている言葉達です。
『内なる言葉』に幅や奥行きを持たせることで、言葉に重みや深さが出て相手が受け入れようと感じる言葉を発することが出来るようになります。
さらに理解を深めるために、、、
私たちが言葉を生み出す2段階のプロセスについてみてみましょう。
言葉を生み出す2つのプロセス
①「内なる言葉」で意見を育てる
人間はあらゆることの思考、感情が頭に浮かぶ際は必ず内なる言葉を伴っています。
言葉を使わずに考え事をしている人なんていませんよね。
まさに考え事をするときに使う言葉が、“内なる言葉”です。
内なる言葉による自分自身との対話は、考えを広めたり、 深めたりすること同義で、それを繰り返していると、自分の意見が育っていきます。
自分が何を考えて何を伝えたいかの輪郭が明確になるということです。
②意見が「外に向かう言葉」に変換される
外に向かう言葉は一般的に“言葉”と呼ばれるものを指します。
他者との接点の役割をし、意思疎通を行う道具です。
内なる言葉とは違い、情報を受け取る他者が存在しています。
私たちが誰かの“外に向かう言葉”に対して感じる「重さ・軽さ」「深さ・浅さ」の印象は、内なる言葉を使ってどれだけ広範囲で掘り下げたかに影響されています。
仮に耳に届く「外に向かう言葉」だけを鍛えようとし、言葉の巧みさを手に入れたとしても、相手には薄っぺらな言葉を届けるだけになってしまいます。
口だけ達者な内容のない人物になりかねないので注意が必要です。
内なる言葉の充実
人間は考えていることしか口にできず、言葉は思考の上澄みです。
言葉が湧き出てくる源泉を豊かにしておかなければ、相手に伝わる言葉を発することは出来ません。
日ごろから内なる言葉と向き合うことでで、言葉に深さ・重さを付加し、「伝えたいこと」「伝えなければならないこと」への気持ちを高ぶらせます。
内なる言葉を充実させる具体的な2つのこと
内なる言葉を意識する
まずは内なる言葉の存在を意識することから始めてみましょう。
内なる言葉を意識することは、自分自身と向き合うことです。
「こんなとき自分はこんな事に考えていたのか!」
「こんなことが悲しいんだ!」
「こんなことに怒っているんだ!!」
という具合に、自分の思考や感情の動きに対して第3者的な視点を持つことが、思考を拡げ、確実に外に向かう言葉に影響を及ぼします
内なる言葉で自分思考を深めて外に向かう言葉へと変換させるようになると、自分の中から湧き出てくる言葉を伝えるようになり、相手の胸に響き、納得や共感を得やすくなります。
「人が動きたくなる」言葉
最高レベルに相手に自分の言葉が伝わると、人は「動かされる」のではなく「動きたくなる」
状態にさせられてしまいます。
人の心を動かす最大の要因は本人の本気度や使命感が感じられる“体温のある言葉”です。
“体温のある言葉”を発するには、自分の考えに確固たる自信を持つ必要があり、その過程を歩むには内なる言葉に意識を向けることは不可欠です。
自分は本当に何をしたいのか。何を訴えたいのか。他人に伝える前に自分の中でしっかりと意見を育てるのです。
その結果、共感や共鳴をした人間が支えてくれ、連いてきてくれるのです。
逆を言うと、口だけであったり、利己的な面が見え隠れすると、聞き手は敏感に感じ取り、一気に心の距離を空けてしまいます。
が、現実社会では内なる言葉が無視されていることが多いのではないでしょうか。
会社組織では、発信者の感情関係なしに、会社の意向を指示することが多いためです。
それでは本当の意味で社員と会社が分かり合うわけがありません。
ま と め
自分がいかに“言葉”というものをないがしろにしてきたか、私は猛省しました。
言葉を扱うプロである筆者の考えかたや姿勢に驚きの声を上げて夢中に本にのめり込みました。
1.コミュニケーションに4段階がある
2.内なる言葉と向き合う
3.聞き手が“動きたくなる”ことが本当の言葉の力
伝わり方を人間の内側の状態から論理的に分析している視点が、非常に新鮮で納得してしまいました。
日頃のコミュニケーションを振り返ると、聞き手・話し手、どちらの場合でも2~3つ目の段階のことが多いなと感じています。
同時にその事実は“納得”以上の伝わる言葉を発することの重要性を示しています。
そして、、、
内なる言葉の存在を知り、内なる言葉を意識すること。
これが伝える力を高める肝です。
伝える言葉を発することだけではなく、“内なる言葉”と向き合うことは、生きていく上でも必須なスキルですので、是非とも習慣化したいですね。
私も日常生活の中で、自分がなぜ嬉しいと思ったのか、嫌だと感じたのか、以前よりも詳細を気にするように心掛けています。
まだまだ聞き手が動きたくなるような言葉を扱えるような人間になっていませんが、
自分の伝え手としてのレベルが上がって、周囲にも高レベルな発信者との交流関係が多くなるような人生に出来たら、最高だと思っています。
言葉の持つ力、まだまだ勉強のしがいがありそうです。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。